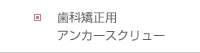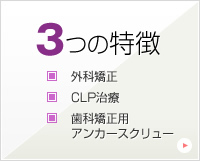CLPとは口唇裂口蓋裂のことを指します。口唇裂口蓋裂は唇や上あごが割れた状態で生まれてくる最も頻度の高い先天異常です。九州大学病院では口腔外科・矯正歯科をはじめ多くの科でチームを組み、患者さんの成育を支援し、治療を行っています。また福岡親子の会「つばさ」と連携して、勉強会・親睦会など患者家族相互や医療スタッフとの情報交換活動を行っています。
治療のステップは5段階

周産期から口唇形成術
九州大学病院では、哺乳床(ホッツ床やNAM)といって、ミルクが鼻にこぼれないようにする義歯を入れます。誕生の日に、小児歯科医が上顎の型をとって哺乳床を作ります。口唇の手術のこともありますから口腔外科(電話:092-642-6445)にすぐにご連絡ください、小児歯科の先生と連携してご相談します。3か月ごろに口唇の手術をします。

口蓋形成手術まで
口蓋裂がある赤ちゃんは、1歳半頃にその閉鎖手術を行います。
手術後は、口蓋が十分動き、正しい発音ができるように言語訓練が必要です。

乳歯列期
3才後半から言語訓練と平行して、矯正の先生が顎の発育と噛み合せの管理を行いま す。九州大学病院では4才から半年毎に 定期検診を行い、問題が生じてきたら治療に取り掛かる体制を取っております。
成人になるまで長い期間のお付き合いになるので、子供さんの負担を考えて、装置を入れる期間を短くするよう努めていきます。

混合歯列期、学童期
小学校1~2年生で上顎の真ん中の歯(中切歯)が生えてきた時、 破裂がある側の歯は捻じれて生えてきます。
下顎の前歯の歯並びを障害する時は装置を入れて捻じれを除去します。 その後は定期検診を続けます。
次に、破裂に対する、腸骨(腰の骨)移植の時期を検討します。犬歯が生えてくる直前が良いと考えています(おおよそ小学校4~5年生頃)。骨移植の1年前に狭くなった上の歯列を正常な形まで拡大を行います。骨移植後1~2か月の内に、歯に装置(ブラケッ ト)をつけて、歯を移植骨の方へ移動して歯列を作り上げます。この治療は2~3年かかります。
鼻の変形の程度がひどければ、修正手術の必要があります。

永久歯列期、中学生から成人になるまで
中学校~高校生にかけて、 最終的な歯の排列を行い咀嚼できるようにします。
鼻や口唇の変形のある場合は、再形成手術をこの時期に行います。
また、高校3年生あるいはそれ以降に、歯の先天的な欠如など種々の要因によって、ブリッジなど人工歯を使って咬合を完成させることもあります(補綴的処置)。
上顎骨の発育が異常に悪い場合や、下顎骨の成長が非常に大きい場合には、 外科的矯正治療によって顔貌を改善する方法もあります。