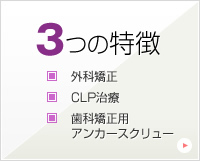歯科矯正治療とは、歯やあごの骨に力をかけてそれらをゆっくりと動かすことで、悪い歯並びや咬み合わせ(不正咬合)を整え、正しく機能的な咬み合わせ(正常咬合)を獲得し、さらにはバランスのとれた口元を作り出す治療です。
正しく機能的な咬み合わせを獲得することは、「咬む」という機能を向上させるだけでなく、う蝕や歯周疾患、顎関節症の予防のために必要です。また、歯並びは口元の美しさや表情の成り立ちとも深い関わりがあります。不正咬合は、口腔周囲の習癖(指しゃぶり、爪咬み、舌癖など)や、耳鼻科疾患(アデノイドや慢性的鼻閉など)に起因する口呼吸などとも関連があり、放っておくと顔つきまでも変えてしまいます。
不正咬合に伴うリスクと障害について
かみ合わせの悪い状態いわゆる不正咬合のままで放っておくと、う蝕や歯周疾患のリスクが高くなったり、様々な障害を引き起こす可能性があります。不正咬合のタイプは様々で、症状や程度も人によって大きく異なります。
下にそれぞれの不正咬合に対する代表的な障害やリスクを挙げています。矯正治療を希望される場合は、自分の不正咬合のタイプや症状を把握し、それに合った納得のいく治療法を見つけることが大切です。
不正咬合には次のような症状に伴う代表的な障害やリスクが挙げられます。

上の前歯が出ている(上顎前突)
咀嚼障害
外傷のリスク
審美的な問題
呼吸障害のリスク
嚥下異常

受け口である(反対咬合)
咀嚼障害
発音障害
審美的な問題

上下の前歯が出ている(上下顎前突)
咀嚼障害
審美的な問題
う蝕・歯周病のリスク

歯がでこぼこしている(叢生)
咀嚼障害
審美的な問題
う蝕・歯周病のリスク

すきっ歯である(空隙歯列)
咀嚼障害
発音障害
う蝕・歯周病のリスク

上下の歯列が横にずれている
(交叉咬合)咀嚼障害
成長発育への影響
顎関節への影響

咬み合わせが深い(過蓋咬合)
咀嚼障害
顎関節への影響
審美的な問題

上下の歯が咬み合わない(開咬)
咀嚼障害
発音障害
顎関節への影響
呼吸異常
嚥下異常

歯が骨に埋まって生えてこない
(埋伏歯)咀嚼障害
発音障害
審美的な問題
歯根吸収
自由診療となる矯正治療について
当科で診療している患者さんの約半数は一般的な不正咬合に対する矯正歯科治療をお受けになっており、この治療は自由診療となります。自由診療の対象となる不正咬合における矯正治療上必要な抜歯も、保険適用外の診療となりますので、ご注意下さい。
残りの約半数は、「別に厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療、ならびに顎の外科手術を要する顎変形症の手術前、手術後の矯正歯科治療、および前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするもの)をお受けになる患者さんで保険診療の対象となります。
矯正治療おいて予想される危険性・副作用・合併症について
1. 矯正装置の装着後及び着脱動作中に、歯肉、舌、頬及び唇に、擦り傷又は痛みが生じる場合があります。
2. 矯正治療開始直後及び途中に歯の圧痛を経験する場合があります。
3. 矯正装置の装着が、一定期間、患者さんの発語に影響を与える場合があります。
4. 治療過程のいずれかにおいて、咬合状態が変化し、患者様によっては一定期間、不快感を感じる場合があります。
5. 矯正装置の使用により、頭頸部の関節及び筋肉、耳それぞれにおいて障害(運動、感覚、疼痛)が生じる場合があります。
6. 治療中、歯の変色及び着色が生じる可能性があります。
7. 矯正装置を使用した治療完了後、歯の位置が移動する場合があります。
8. 治療期間中は、虫歯や歯周病への対策を積極的に行う必要があります。
9. 矯正治療を中断した場合でも、治療前の状態に戻すことはできません。
10. 歯根の屈曲・吸収
歯の移動に伴い、歯根の形成が不十分になったり、歯根が吸収(短くなる)あるいは屈曲したりすることがあります。その後の歯の寿命に影響を与えることは殆どありませんが、レントゲン検査で判別できる歯根吸収は、程度の差こそあれ矯正治療を受けた患者さんの約70%で認められます (Orthodontics Waves 57 (5), 1998)。歯の寿命に影響を与える等、臨床的に問題になる可能性があるほどの歯根の屈曲・吸収がみられた場合、矯正力を作用させない休止期間を必要に応じて6か月ほど設定し、経過を観察してから再開することがあります。場合によっては治療計画を変更、あるいは治療を中止することがあります。
11. 歯髄壊死
非常にまれですが、歯の移動に伴い歯髄壊死(歯の神経が死ぬ)が起こることがあります。
12. 歯肉退縮
歯の移動に伴い、歯ぐきが下がり歯が長く見えるような状態(歯肉退縮)が発生することがあります。多くの場合、見た目に影響を及ぼしたり、歯周病にかかりやすくなったりするような、大きな歯肉退縮は起こりませんが、程度の差こそあれ、矯正治療後に歯肉退縮がみられる患者さんの割合は治療終了時約7%です (American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 143 (3), 2013)。 特に、顎裂骨移植や歯を抜いた場所の両脇にある歯に関しては、歯ぐきの量が不足し歯が長く見えるようになることがあります。
13. 顎関節症
もともと顎関節に異常がある患者さんや、関節の適応力が弱い患者さんでは、顎関節にカクカクといった音や痛みなどの症状 (顎関節症)が出ることがあり、矯正治療後の約30%の患者さんにおいて症状を認めます (日本顎関節学会雑誌 22 (1), 2010)。痛みが認められた場合には、経過観察を含めた適切な対処が必要です。
14. 眼球の損傷
治療の過程でヘッドギアを用いる場合に、ネックストラップもしくはヘッドキャップを外さずに口の中から口腔内装置を引っ張り出すと、手が滑って装置の先端が目に刺さり、失明する危険性があります。装置を外すときは、必ず、先にネックストラップもしくはヘッドキャップを外して下さい。なお装置の詳細な着脱方法については、装置装着時に改めて説明します。
以上に挙げた合併症は、生命に関わる事態になる可能性があります。仮に生じた場合は、最善の処置・治療を行いますが、治療を行う上で、一定の頻度で起こる可能性があるものです。その際の医療費については、不可抗力によって発生し通常の保険診療が可能なものは健康保険を用いたものになります。それ以外のものは、都度病院にて対応を協議して決定いたします。
治療において予想される危険性・合併症の全てを把握すること、また全てを記載することはできません。記載していない合併症が起きることがあることをご理解ください。
問い合わせ先
九州大学病院 矯正歯科
福岡市東区馬出3-1-1 九州大学病院外来棟5階
月~金曜日 9~17時
TEL 092-642-6460 FAX 092-642-6398